今回は、生活介護について解説します。
放課後等デイサービスなどの次の展開で「生活介護」を考えている方は必見。
【サービス内容】
生活介護は、主に昼間、日常生活の支援をするサービスで、自立の促進、生活の改善、身体機能の維持向上を目的としたサービスを提供します。
- 入浴、排せつ、食事等の介助
- 創作的活動、生産活動の機会の提供
- 身体機能や生活能力の向上のために必要な援助
- 調理、洗濯、掃除等の家事
- 生活等に関する相談、助言
- その他日常生活上の支援
生産活動の機会提供など、就労につながる支援を行うこともあり、工賃を発生させることもあります。
※日常生活を支援するサービスなので、メインは就労を目的としたものではないことに注意
【利用対象者】
安定した生活を営むため、常時介護等の支援が必要な方で次に該当する方
(1) 障害支援区分が区分3(障害者支援施設に入所する場合は区分4)以上
(2) 年齢が50歳以上の場合は、障害支援区分が区分2(障害者支援施設に入所する場合は区分3)以上
(3) 障害者支援施設に入所する方であって障害支援区分が区分4(50歳以上の場合は区分3)より低い方のうち、指定特定相談支援事業者によるサービス等利用計画案の作成の手続きを経た上で、市区町村が利用の組み合わせの必要性を認めた方
※ (3)の方のうち以下の方については、原則、平成24年4月以降の支給決定の更新時にサービス等利用計画案の作成を行なった上で、引き続き、生活介護を利用することができます。
・法の施行時の身体・知的の旧法施設(通所施設も含む)の利用者(特定旧法受給者)
・法の施行時に旧法施設に入所し、継続して入所している方
・平成24年4月の児童福祉法改正の施行の際に障害児施設(指定医療機関を含む)に入所している方
【人員配置】
・管理者(兼務可)1以上
・サービス管理責任者 常勤1以上(60人以下)
・生活支援員 1以上(1名以上は常勤)
・理学療法士、作業療法士、言語聴覚士・・・日常生活を営むのに必要な機能の減退を防止するための訓練を行う場合は、訓練を行うのに必要な数
・看護職員1以上
・医 師(嘱託医可)
※生活支援員・理学療法士・作業療法士・言語聴覚士、看護職員の総数が常勤換算で以下のとおり。
・平均障害支援区分が4未満 6:1
・平均障害支援区分が4以上5未満 5:1
・平均障害支援区分が5以上 3:1
【設備基準】
・作業訓練室・・・サービス提供に支障のない広さを備えること(1人あたりの面積は指定先により異なる)
・相談室
・多目的室(相談室と兼用可)
・事務室
・洗面所、トイレ
・その他運営上必要な設備
※人員基準、設備基準ともに指定先により独自ルールの可能性あり要確認
Instagramの関連記事はこちら
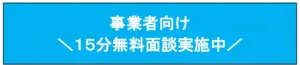
河合(ふくふる福祉行政書士事務所)の面談は、こちらをクリック

