保育所等訪問支援は、保育所その他の児童が集団生活を営む施設に通う障害児又は乳児院その他の児童が集団生活を営む施設に入所する障害児につき、当該施設を訪問し、障害児以外の児童との集団生活への適応のための専門的な支援を行います。
<訪問先の例>
・保育所
・幼稚園
・認定こども園
・小学校
・中学校
・高等学校
・特別支援学校
・乳児院
・児童養護施設
・その他児童が集団生活を営む施設として市町村が認める施設
→放課後児童クラブ、児童館、中学校や高校などが想定される
事業展開として多いパターンが、
1,児童発達支援の運営が安定的になり、保育所等との連携が取れてきた
2,保育所等訪問支援を多機能型で追加指定を受ける
といった流れ。
例外はありますが、頻繁に保育所等訪問支援を使うというよりは、児童発達支援の支援をより手厚くしていくために、保護者や市町村、保育所等から求められて指定をとることになり、補完的に活用されることが多い印象ではあります。
放課後等デイサービスは、学校への訪問のハードルが高く、連携がしっかり取れていないと難しい側面がありますので、学校との関係構築がより重要になってきます。
児童発達支援、放課後等デイサービスのいずれも、保育所等訪問支援をスタートするための目安としては、まずは、関係機関連携加算を上手く活用できていると入りやすいかもしれません。
<支援の対象>
✅ こども本人に対する支援
訪問先施設や家庭での生活に活かしていくために行われるもので、訪問先施設に引き継がれていくもの。
本人が集団生活の場で安全・安心に過ごすことができるよう、訪問先施設における生活の流れの中で、集団生活への適応や日常生活動作の支援を行うことが必要であるとされています。
✅ 訪問先施設の職員に対する支援
訪問先施設のこどもに対する支援力を向上させることができるよう、こどもの発達段階や特性の理解を促すとともに、発達段階や特性を踏まえた関わり方や訪問先施設の環境等について助言を行う。
「訪問先施設の職員に対する支援」においては、訪問先施設の意向を踏まえるとともに、訪問先施設の理念や支援方法を尊重する姿勢が重要とされています。
✅ 家族に対する支援
障害のあるこどもを育てる家族が安心して子育てを行うとともに、安心して
保育所等に通わせることができるよう、保護者に対し、訪問先施設におけるこども本人の様子や、訪問先施設の職員の本人への関わり方などを含め、提供した保育所等訪問支援の内容を伝える。
こども本人の状況や家庭の状況等を踏まえるとともに、保護者の気持ちを受け止め、こども本人と保護者との相互の信頼関係を基本に、保護者の意思を尊重する姿勢が重要とされています。
訪問頻度
2週間に1回程度、ひと月に2回程度の支給量を基本と想定して支給決定がなされます。
ただし、必ずしもではなく、支給決定日数は市町村によってまちまちですし、個々の状態に応じて柔軟に対応していくする必要があるとされているので、最終的には市町村の判断になってきます。市町村の理解が薄い場合やその他の事情によっては、極端に支給決定日数が少なかったり、逆の場合もあったりします。
訪問時間
30分以上必要。
ただし、保育所等を訪問し、こども本人に対する支援や訪問先施設の職員に対する支援、支援後のカンファレンス等におけるフィードバックを行うため、本人の行動観察や、集団生活への適応や日常生活動作の支援、訪問先施設のこどもへの支援力向上のための支援を丁寧に行うものであることを踏まえると、次のようなものになることが基本と考えられるとされています。
1,本人や訪問先施設の職員に対する支援は1時間程度
2,訪問支援後のカンファレンス等を通じた訪問先施設への報告は30分程度
トータル1時間30分は滞在しているのが、一般的なイメージではあります。
また、「1」「2」を連続して行えない場合は、「2」に関してはオンラインなどで時間をずらして行うことも考えられたりします。このあたりは、訪問先施設の状況によって異なるため、連携をとり調整していけるといいでしょう。
アセスメントのポイント
<こどもに関する情報>
【発達の状況】
・生活リズムの把握
・運動発達
・日常生活動作の状況 過敏さなど感覚面の特徴
・認知発達
・対人・コミュニケーション 遊びの特徴
・遊びの特徴
【生活の状況】
・登園(登校)・降園(下校)の時間
・登園(登校)方法:保護者の送迎、送迎用バス(スクールバス)の利用等 ・他の支援サービスの利用状況
□ 地域との交流の状況
【保育所等での生活の様子】
・日常生活動作:食事、排泄、着替え等
・行動の様子:集中力、落ち着き、他者への関わり、パニック、こだわり、その他の 行動上の課題等
・対人関係:友達との関係、先生との関係等
・集団生活:集団参加、集団行動等
・遊び:自由時間・休み時間の様子、自由遊び・設定遊びの様子、遊び相手、遊びの内容等
【こどもの意見】
・こども自身の困りごと
・自分の生活の場において訪問支援が行われることについて
□ 保育所等への移行に関する意向
<訪問先施設に関する情報>
【保育所等の職員からの情報】
・支援の対象となるこどもの特性への理解
・こどもについて困っていること、課題と感じていること
・現在行っている支援方法
・こどもが成長してきていること
・クラスの課題
・保護者への思い
・保育や授業内容などの特色、施設の方針
【保育所等の環境】
(物理的環境)
・クラスの規模:こどもの人数、支援の対象となるこどもの有無・人数
・担任の保育士や教師の人数、支援員の有無・人数
・施設の作り、保育室や教室の位置
・1日の流れ、時間割
・日常の生活や遊び、特色のある取組、行事
□ 地域との交流の状況
(人的環境)
・保育所等の雰囲気
・保育・教育方針の特徴
・他のこどもとの関わり、他のこどもの様子
・他のクラスの担任等を含めた職員との関わり
今回は、訪問頻度・支援時間・アセスメントの視点を主に取り上げてみました。現在、保育所等訪問支援を運営されている方やこれから予定されているは、特に令和6年度にまとめられた保育所等訪問支援ガイドラインも合わせて読み込んでおきましょう。
Instagramの関連記事はこちら
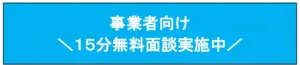
河合(ふくふる福祉行政書士事務所)の面談は、こちらをクリック

