障害のある方の働き方
「障害者雇用と一般雇用のどちらを選べばいい?」
「そもそも障害者雇用と一般雇用の違いは?」
☑︎ 一般雇用
障害の有無関係なく就労できる
☑︎ 障害者雇用
障害者の職業の安定を図ることを目的されており、企業規模によって、障害者の雇用率が決まっていたり配慮された働き方がしやすくなる
今回は、一般雇用と障害者雇用3つの違いについて取り上げていきます。
①収入の違い
障害者雇用は、一般雇用に比べると収入が低くなりがち
障害者雇用の1ヵ月の平均賃金
身体障害者・・・23万5千円
知的障害者・・・13 万7千円
精神障害者・・・14 万9千円
中には年収300万円台の企業もあります。
※参考資料:厚生労働省「令和5年度障害者雇用実態調査結果報告書」
②配慮の違い
・障害者雇用促進法
・合理的配慮の提供義務
・障害者雇用率制度(法定雇用率)
企業の障害への理解や労働力の確保、国の施策などもあって積極的に進められています。
障害者雇用促進法
・法定雇用率制度
・差別禁止と合理的配慮の提供義務
・障害者職業生活相談員の選任
雇用に関して、均等な機械・待遇の確保・障害者がその有する能力を有効に発揮することができる措置等を講じることが目的
合理的配慮の提供が義務化
令和6年4月1日から事業者への責務となりました
障害がある人の活動が制限されてしまう場合、その制限となるバリアを取り除く
① 行政機関等と事業者が、
② その事務・事業を行うに当たり、
③ 個々の場面で、障害者から「社会的なバリアを取り除いてほしい」旨の意思の表明があった場合に
④ その実施に伴う負担が過重でないときに
⑤ 社会的なバリアを取り除くために必要かつ合理的な配慮を講ずること
ひとり一人の状況に合わせて、相互理解のもとに対応策を検討していきます
③障害者雇用率制度(法定雇用率)
従業員が一定数以上の規模の事業主に対し、従業員に占める身体障害者・知的障害者・精神障害者の割合を「法定雇用率」以上とする義務付けをするものになります。
☑︎ 令和6年4月〜令和8年6月
民間企業 2.5%
国、地方自治体 2.8%
☑︎ 令和8年7月以降
民間企業 2.7%
国、地方公共団体 3.0%
今後も雇用率が上がっていくことになっていくと思います。
障害者雇用で働くための活用制度
☑︎ 公共職業安定所(ハローワーク)
☑︎ 地域障害者職業センター
☑︎ 就労移行支援
☑︎ 障害者就業・生活支援センター
これらの制度を活用や、企業の採用ページへの応募、障害者向けの企業説明会などから検討することができます。
障害者雇用のポイント
良いところ
☑︎ 障害理解がある職場であることが多い
☑︎ 多様性ある組織づくりができる
☑︎ 業務の見直しにより、業務効率化を検討できる
☑︎ ワークライフバランスを見直すきっかけになる
☑︎ 社会的責任を果たし、国からの援助(助成金)もある
注意ポイント
☑︎ 精神障害者保健福祉手帳、身体障害者手帳、療育手帳いずれが必要
☑︎ 一般雇用に比べて求人の数が少なめの傾向
☑︎ 社内にマッチする仕事の選定、指導者育成
☑︎ 雇用に対してのノウハウや安全面の配慮の準備が必要
☑︎ 障害特性、適正や能力の把握
一般雇用と障害者雇用と違いを取り上げてみました。
障害を持った当事者が働けるための枠組みをざっくりで良いので知っておきましょう。
Instagramの関連記事はこちら
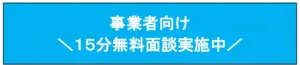
河合(ふくふる福祉行政書士事務所)の面談は、こちらをクリック

