こども基本法(第3条4項)
全てのこどもについて、その年齢及び発達の程度に応じて、その意見が尊重され、その最善の利益が優先して考慮されること
令和6年度より、こどもの最善の利益を保障するため、【こどもの意見の尊重】と【最善の利益の優先考慮】の下で運営基準で次のことが求められるようになりました。
・個別支援計画の作成
・個別支援会議の実施
・支援の提供
※障害児通所支援事業所&障害児入所施設
具体的には・・・
こどもが自立した日常生活又は社会生活を営むことができるよう
・個別支援計画の作成
・適時に、日々の支援の内容や将来の生活に関して、こどもや保護者の意向を丁寧に把握
・その意思をできる限り尊重するための配慮をする
個別支援計画の作成においては、サービス担当者会議への参加や前後で会って意見を聞くことが例として挙げられていますね
例:
・個別支援会議の場にこどもや保護者に参加してもらったり、
・個別支援会議の開催前に担当者等がこどもや保護者に直接会ったりする
こどもの年齢や発達の程度に応じて、様々な形でこどもや保護者の意見を聴くことが求められています。
(言葉以外に身体の動きや表情、発声なども観察し、こどもの意見を尊重する)
こどもとの信頼関係の構築
こどもの意思の尊重・最善の利益の優先考慮に向けて
「意思形成支援」
↓
「意思表出支援」
↓
「意見形成支援」
↓
「意見表明支援」
↓
「意見実現支援」
日常生活や個別面談等を通じてこどもと関わりながら、個別にコミュニケーションをとっていく。
様々な状況
☑︎ 必ずしも言語的なコミュニケーションが可能ではない場合
☑︎ 様々な事情で余暇や文化的活動の経験が限られてきた場合
☑︎ 主体性が育っておらず、意思の表出に関わる意欲が委縮している場合
こどもの育ちについて理解した上で、信頼関係を構築し、愛着を土台として安全・安心な環境の中で、こどもの自己肯定感を育んでいく。
人への期待や信頼感を育み、自分の存在を肯定し、他者との適切な関係を形成するための基礎固め。
意思形成支援
☑︎ こどもが遊びや豊かな活動等を通じて様々な経験を積み重ね、自分が権利の主体であることを理解
☑︎ 様々な選択肢があることを学ぶ
☑︎ 自分で選択する経験を増やしていく
☑︎ 日常の遊びや活動、生活場面の中で、こどもが表出したことに応答
☑︎ こどもが受け止められたと実感し、また表出したいと思えるようなコミュニケーション
これらの繰り返しの中で、こどもの自己肯定感を育んでいく。
最後に参考資料としてあげる手引きには、活動場面における配慮や選ぶことや活動場面における配慮事項や選ぶ機会の提供例が挙げられています。
意思表出支援
☑︎ こどもの独自の意思表示の方法を理解し
☑︎ 育まれた意思が、言葉やそれ以外の方法で表出されるように工夫し支援
意見形成支援
☑︎ 意思表出支援と同時に、様々な経験を通してを積み重ねていく。
意見表明支援
☑︎ こどもの形成された意見を言語化し、こどもにその内容を必ず確認
☑︎ こどもが思っていることを他の人にもわるように言語化・通訳
意見実現支援
☑︎ こどもが表明した意見を反映していくように努める
☑︎ こどもが自ら判断し行動することを支えていく
まとめ
【こどもの意見の尊重】と【最善の利益の優先考慮】をもとに対応が必要なこと
☑︎ 個別支援計画の作成
☑︎ 個別支援会議の実施
☑︎ 支援の提供
こどもの年齢や発達の程度に応じて、こどもや保護者の意見を聴くことの例:
・個別支援会議の場にこどもや保護者に参加してもらう
・個別支援会議の開催前に担当者等がこどもや保護者に直接会ったりする
※子どもの年齢や発達の程度に応じて対応
参考資料:
・令 和6年8月9 日事務連絡通知 「障害児支援におけるこどもの意思の尊重・最善の利益の優先考慮の手引き」について
・障害児支援におけるこどもの意思の尊重・最善の利益の優先考慮の手引き
Instagramの関連記事はこちら
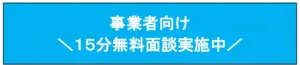
河合(ふくふる福祉行政書士事務所)の面談は、こちらをクリック

